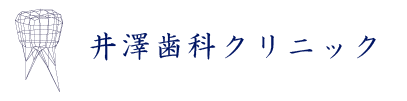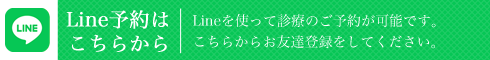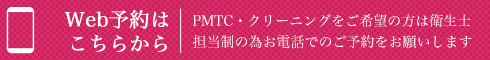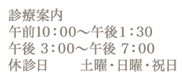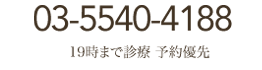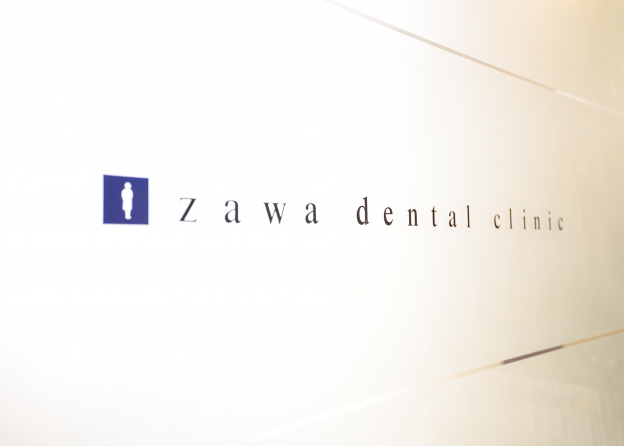生活を行ううえで、どうしても歯の表面についてしまうステイン(着色汚れ)。
ステインを予防・除去する為には、その原因と正しい対処方法を知ることが必要です。
ここではステインが付着する原因と正しいステインケアについて解説します。
〜ステインとは?〜
ステインとは食物中に含まれるポリフェノールの色素と、歯の表面を覆っているペリクルというタンパク質の膜が結びついたものです。
ポリフェノールは苦味や色素成分を含み多くの植物に存在します。
また、タバコの成分であるタールは褐色に変化するうえ、唾液中のカルシウムと結びつくため強固に付着する色素へと変わります。
この着色汚れは毎日歯磨きをしていても、特に磨きづらい部分に少しずつ付着し、黄ばんだり、くすんだりさせていきます。その付着スピードも食生活による為、人それぞれです。
〜ポリフェノールが多く含まれる食品〜
ポリフェノールは抗酸化作用が強く、活性酸素などの有害物質を無害な物質に変える作用や、ポリフェノールの種類によっては、動脈硬化予防、血圧低下、視力回復、美肌効果、毛細血管強化作用、肝臓保護作用等の身体に良い効果があるとも言われています。
・赤ワイン
・ブルーベリー
・ぶどう
・緑茶
・紅茶
・ココア
・チョコレート
・玉ねぎ
・春菊
・蓮根
・カレー
・コーヒー 等
〜ステインが付着しやすい人〜
①唾液が少ない
唾液には歯の汚れを洗い流す自浄作用があります。ストレスや病気、薬の副作用により唾液の出が少なく、ドライマウスになっている場合は、飲み物や食べ物の色素が残ってしまいステインになりやすくなります。
唾液の出を良くする為に、ガムを噛む、口腔内をマッサージする等の唾液腺を刺激する行動や、口全体に含むようなこまめな水分補給、口腔保湿剤の使用するなども対策として効果です。
②口呼吸
口呼吸や常に口がポカンと開いていると、唾液が充分に出ていたとしても乾燥状態になります。
特に上の前歯は唾液腺が近くにない為、乾燥しやすくステインが付きやすくなってしまいます。
また、虫歯や歯周病のリスクも高くなる為、できるだけ鼻呼吸を心がけ、鼻に鼻炎等の問題がある場合は耳鼻科でご相談されてもいいかもしれません。
③ポリフェノールの摂取
上記でも記載しましたがポリフェノールは身体に良い作用が沢山あります。特にポリフェノールが多く含有されている食品を摂取した後はすぐに歯を磨く、又はすぐに磨けない状況であれば水でぶくぶくうがいをするだけでも付着率を軽減することができます。
〜ステインの付着を防ぐために〜
ステインは時間の経過と共に歯の表面に蓄積される為、毎日こまめに落とすことが大切です。
- セルフケアで出来ること
歯ブラシの当て方は基本的には虫歯、歯周病ケアと同様です。小刻みに動かし歯周ポケット内、歯間部、くぼみに毛先を入れ込みます。その際、歯にブラシ圧をかけ過ぎないように気を付けて下さい。
仕上げに前歯の口唇側に歯ブラシを縦にあて、上下に動かし毛先を更に歯間の細部まで当てましょう。
また、歯間ブラシやデンタルフロスを併用するとステインの付着予防だけでなく、虫歯、歯周病予防にも効果的です。
歯磨剤選びのポイントですが、顆粒が粗いすぎないものを選んで下さい。
粗いものの方がステインが落ちるイメージがあるかと思います。一時的にはステインは落ちますが、歯の表面に傷がつくため、ステインが再着色しやすくなります。
- プロフェッショナルケアで出来ること
既に付着しているステインはご自身では取らないでください。
セルフで落とす道具も販売されていますが、粗い粒子の材料が多くやはり擦り落とすことになる為、歯の表面に傷がつい逆にステインが付着しやすくなります。
既についてしまったステインに関しましては知識を持ったプロにお任せください。
ステインを再付着しづらくする方法としてPMTCというクリーニングがあります。
P・・・professional
M・・・mechanical
T・・・tooth
C・・・cleaning
「専門家による機械的な歯面清掃」という意味です。
虫歯、歯周病予防効果はもちろんですが、特別な道具で歯の表面の傷をなめす為、繰り返し施術していくことでステインが付着しづらくなります。
さらに高濃度のフッ素塗布も行うスペシャルケアです。
ステインが気になる方だけではなく、虫歯や歯周病のリスクの高い方、矯正中の方、忙しく自分に時間がかけられない方にもおすすめです。
ご参考になりましたでしょうか。
さぁ、にっこり笑ってスマイル生活を送りましょう!!